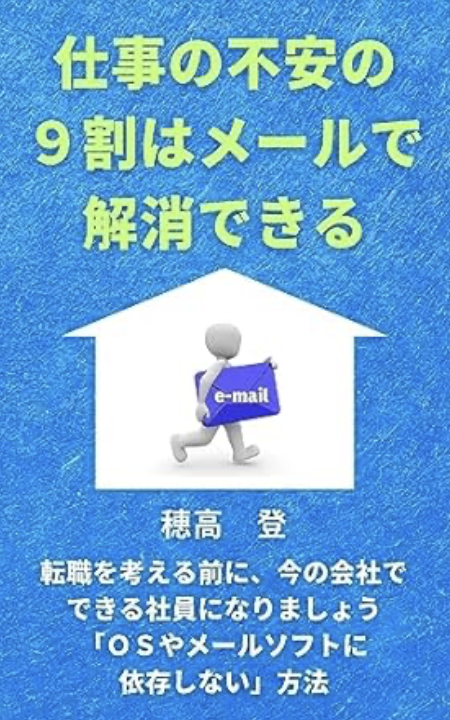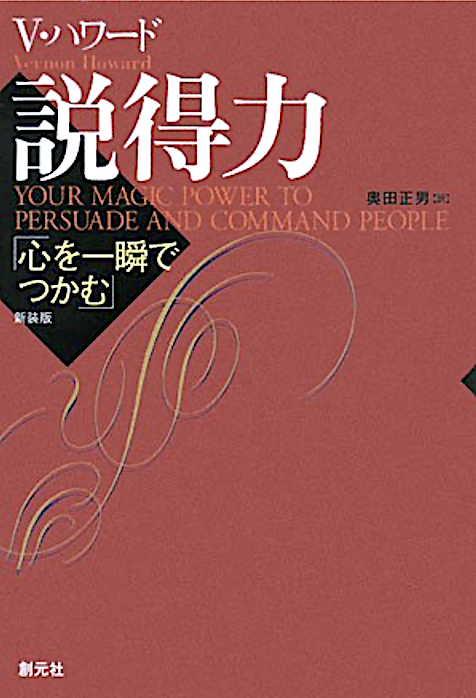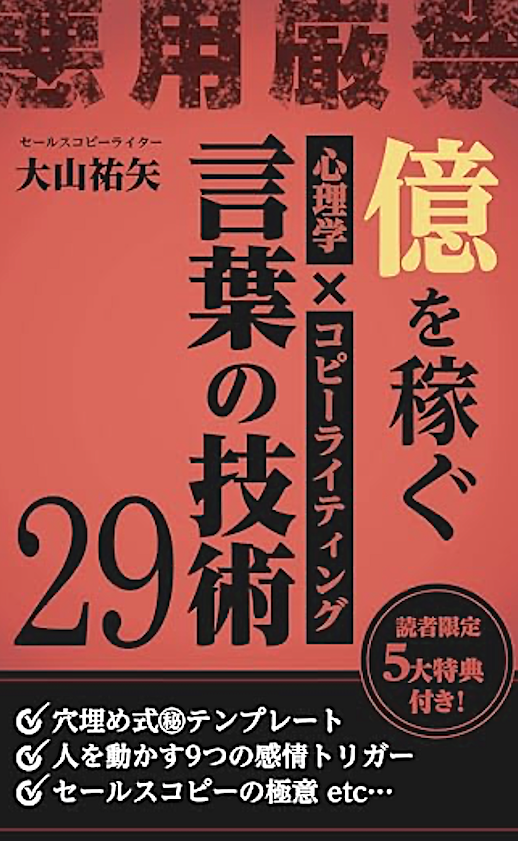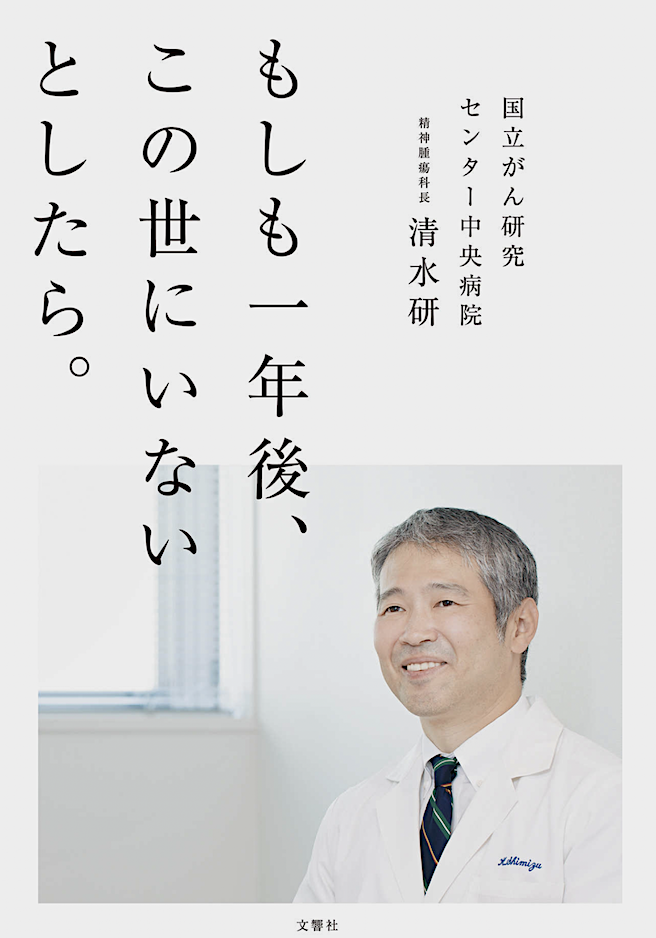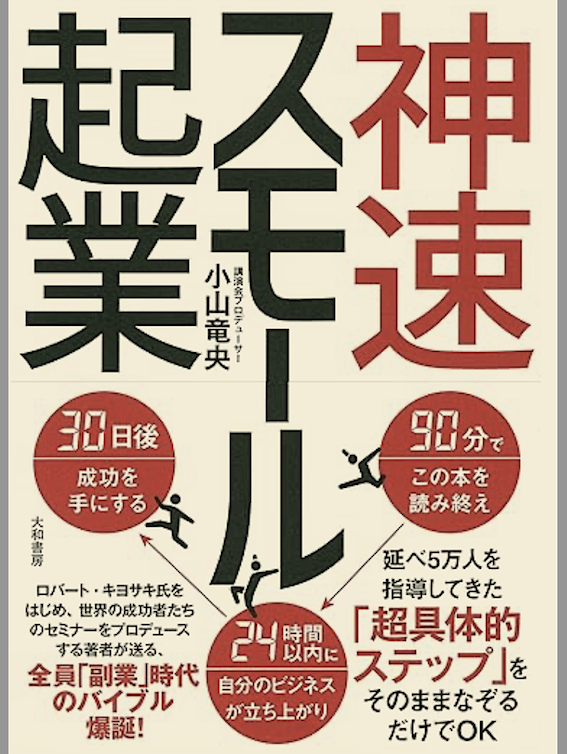私が図書館から本を借りる目的は、
主に2つです。
1.高価で自分では買えない
本を読むため
2. 手元に残しておくべき本か
どうかを確かめるため
1については、
「この本が気になる」と思っても、
数万円もする本だと、
頻繁には買えませんから。
2については、
今まで、本を買ってみたけれど
「失敗した…」と思って
読まなかった本がたくさんあったから。
そこで、実際に借りた本を読んで、
本を買うようにしているんです。
そうすれば、失敗することは
無くなりますので。
なので、借りて来た本を、
隅から隅まで読むことは、
ほとんどありません。
買って手元に置いておきたい本かどうかを
確認することが目的なので…汗
□中古本を買う時の注意点
本の状態の説明が「非常に良い」と
書いてあったとしても、
稀に、マーカー線だらけの本も
届くことがあったりする…汗
こればかりは、相手と自分の
認識の違いなので、
どうしようもありません。
だから、相手を選ぶ願力も
必要になってくるのです。
今まで、結構たくさんの本を借りましたが、
基本的に、図書館から借りて来た本は、
除菌シートで周囲を綺麗に拭いて、
半日ほど陰干ししてから
読むようにしています。
そして返す時にも除菌シートで
拭いてから返しています。
つまり、私が本を借りる度に、
図書館の本が綺麗になって行くんです。